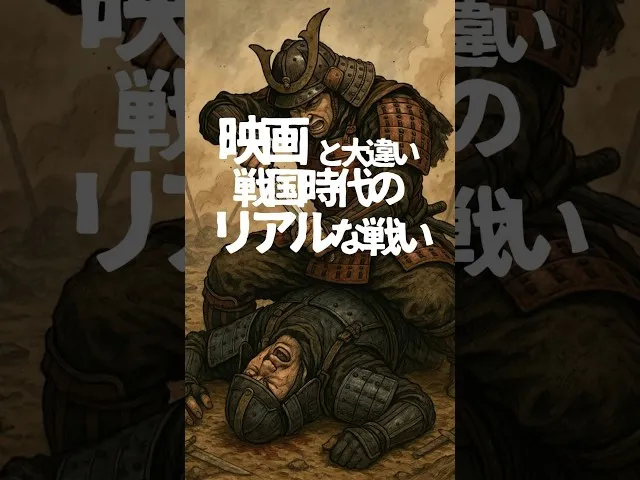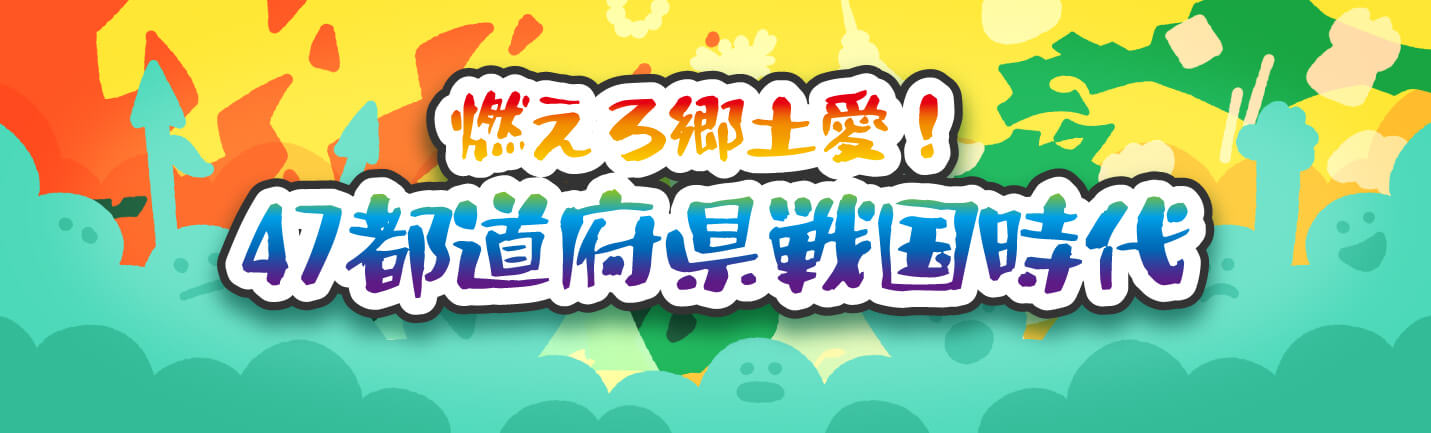映画で見る戦国時代の戦いは華やかですが、実際の合戦は鎧の隙間を狙う、レスリングのような地味なものだったのです。
この記事の目次
映画とは違う!地味な戦い方が主流だった理由
当時の鎧「当世具足(とうせいぐそく)」は、重さ20kg程度と比較的軽量でしたが、鉄板などで作られていたため防御力が非常に高かったのが特徴です。映画のように刀や槍で斬りつけても、なかなか歯が立ちませんでした。
- 熟練の武者なら鎧を着たまま泳ぐこともできたと言われています。
- しかし、体の動きは制限されるため、映画のような派手なアクションは困難でした。
- 鉄板を使用した鎧には、刀や槍の攻撃が通用しにくかったのです。
狙うは鎧の隙間!レスリングのような白兵戦
鎧の防御力が高すぎたため、敵を倒すには鎧の隙間を狙うしかありませんでした。首回り、脇腹、脇の下といったわずかな隙間を「短刀」で突く必要があったのです。必然的に、相手に密着して抑え込み、動きを封じてから仕留めるという、レスリングのような泥臭い戦い方が主流になりました。
- 敵を抑え込んで動けなくするのが先決でした。
- 鎧の隙間を短刀で突き刺してとどめを刺しました。
- 重い兜を利用し、刀の柄(つか)で相手の兜をガンガン叩き、脳震盪を起こさせて首を取る技も存在しました。
関連記事:大鎧と胴丸と腹巻は何が違うの?上級武士が着用した鎧雑学
【まとめ】戦国のリアルな戦いは「泥臭い」サバイバル
映画のような華々しい一騎打ちとは異なり、実際の戦国時代の戦いは「いかにして強固な鎧を無力化するか」という、地味で泥臭いサバイバル術でした。鎧の重さを利用したレスリングのような戦術こそが、当時のリアルだったのです。
Q&A:よくある質問
Q. なぜ戦国時代の戦いはレスリングのようだったのですか?
A. 当時の鎧「当世具足」が非常に強固で、刀や槍が効きにくかったためです。相手を抑え込んで動きを封じ、鎧の隙間を短刀で突くのが最も確実な戦い方でした。
Q. 鎧はどれくらいの重さだったのですか?
A. 動画で紹介されている「当世具足」は、約20kg程度だったとされています。これは熟練者なら着たまま泳げるほどの重さでしたが、動きはかなり制限されました。
関連記事:桶狭間の戦いで家康が着ている鎧には名前があるの?【どうする家康】
みんなが知りたい!日本の甲冑のすべて 世界に誇る鎧と兜の歴史と見どころがわかる
▼ショート動画も毎日更新中!
「ほのぼの日本史」YouTubeチャンネルもぜひチェック