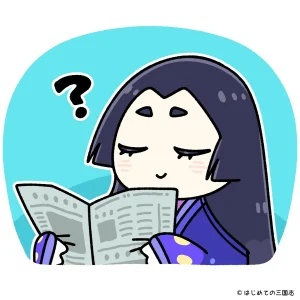江戸時代の武士は、実は暇で貧しく、生活のために「副業」で生計を立てていました。
この記事の目次
なぜ武士は「暇」になったのか?
江戸時代、日本には人口3000万人に対し200万人もの武士がいました。これは、戦国大名が「いつ戦が起きるか分からない」と無理して多くを雇った名残りです。しかし、平和な江戸時代が訪れ戦争がなくなると、多すぎる武士が藩の財政を圧迫し始めました。そこで始まったのが、武士の「パートタイム化」でした。
- 戦国大名が戦に備えて、必要以上に多くの武士を雇っていました。
- 平和な江戸時代になり、武士の仕事が激減すると、彼らの給料(お米)が藩の財政を圧迫しました。
- その結果、出勤体制が「1日働いて3日休み」のような、極端な短時間労働(パートタイム化)になりました。
関連記事:幕府が禁じた春画の魅力とは?江戸庶民が熱狂し、笑いと色気が詰まった歴史
暇だけど「貧しかった」武士の暮らし
「1日出勤で3日休み」と聞くと羨ましく聞こえますが、実態は深刻でした。武士はパートタイマー扱いなので、働かない日の給料はゼロ。つまり、死ぬほど暇であると同時に、収入も非常に少なかったのです。
- 生活に困った下級武士たちは、生きるために「副業」を始めました。
- しかし、武士の体面に関わるとして、顔出しが必要な商売は禁止されていました。
- そのため、朝顔や鈴虫の飼育、野菜作り、傘張り、虫かご作りといった「内職」が主な副業でした。
関連記事:江戸時代の浴場は混浴だった!混浴禁止への驚きの変遷
【まとめ】江戸時代の武士は「戦わない」公務員だった
動画の結論の通り、江戸時代の武士は「暇で貧しく、副業で生活」していました。戦で活躍する姿とは裏腹に、藩の財政事情でパートタイム化され、内職で生計を立てる。それはまるで、現代の公務員や、それ以上に不安定な働き方だったのかもしれませんね。
関連記事:江戸時代からの言葉「やばい」、その意外な起源とは?
Q&A:よくある質問
Q. 江戸時代の武士はなぜあんなに多かったのですか?
A. 戦国時代、大名たちがいつ起こるか分からない戦に備えて、無理をしてでも多くの武士を雇っていたためです。
Q. 武士はどんな副業をしていたのですか?
A. 朝顔や鈴虫の飼育、野菜作り、傘張りなどの内職が多かったです。学問や文芸に自信があれば、寺子屋の師匠や剣術道場を開くこともありました。
関連記事:江戸時代の農民が支払っていた年貢は年1回じゃなかった?
▼ショート動画も毎日更新中!
「ほのぼの日本史」YouTubeチャンネルもぜひチェック









-300x300.jpg)