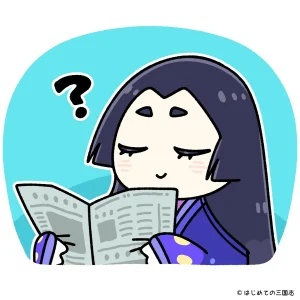もし現代の技術者が鎌倉時代に転生したら、蒸気機関車は作れるのでしょうか?結論から言えば、命がけの「トロッコサイズ」のミニ蒸気機関なら製造可能でした。
この記事の目次
鎌倉時代の技術で「動く」ことは可能
水を沸かし、蒸気の力で車輪を回すという基本的な仕組み自体は、鎌倉時代の鉄鋳造技術でも一応は可能です。しかし、そこには大きな問題が立ちはだかります。当時の鉄は不純物だらけで、非常にもろいものだったのです。
- 蒸気圧が限界を超えると、ボイラーごと大爆発を起こす危険がありました。
- 現代のような安全弁や圧力計もないため、いつ爆発するか誰にも分からない状態でした。
- まさに「命がけ」の乗り物であり、木で動くトロッコサイズが限界だったと推測されます。
関連記事:北条時行の生涯とは?南北朝時代を駆け抜けた武将は何故『逃げ上手の若君』なの?
普及の壁となった「鉄」の強度
なぜ爆発の危険があったかというと、当時の技術では蒸気圧に耐えられる「強い鉄」を作れなかったからです。高圧に耐える強靭な鉄が作れるようになるのは、1855年にベッセマー法が発明されてから、日本では幕末の時代になってからでした。
- 日本には刀を作るため、鉄を叩いて不純物を叩き出す優れた製法がありました。
- しかし、その製法は細長い刀剣には適していても、ボイラーのような大きく複雑な構造物には適用できなかったのです。
関連記事:鎌倉幕府のあった場所は?現在はどうなっている?そもそも幕府って何?
【まとめ】製造は可能だが、普及はしない
結論として、鎌倉時代に蒸気機関車を製造すること自体は、ミニサイズで命がけであれば一応可能でした。しかし、その危険性や製造コストを考えると、実用化され広く普及することは決してなかったでしょう。
関連記事:日本は鎌倉時代からローン社会だった!土倉で借金をしていた鎌倉時代の庶民生活
Q&A:よくある質問
Q. 鎌倉時代に蒸気機関車が作れない最大の理由は何ですか?
A. 当時の鉄は不純物だらけでもろく、蒸気圧に耐えられず大爆発を起こす危険があったためです。安全弁や圧力計もありませんでした。
関連記事:指切りげんまんの由来が怖い!驚きの由来と収入の関係
Q. 強い鉄が作れるようになったのはいつ頃ですか?
A. 1855年(日本の幕末)にベッセマー法が発明されてからです。それにより、蒸気機関に耐えられる強度の鉄が製造できるようになりました。
関連記事:承久の乱、幕府が勝ったのは尼将軍演説のお陰「だけ」ではなかった?
▼ショート動画も毎日更新中!
「ほのぼの日本史」YouTubeチャンネルもぜひチェック







に乗るkawausoさん-300x300.jpg)