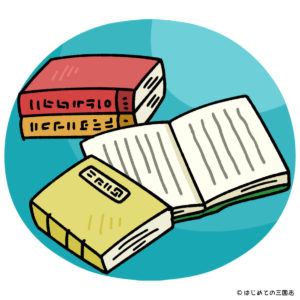日露戦争で勝敗を決めたのは、大砲でも銃剣でもなく「兵站」でした。影の戦場で何が起きていたのか、Short動画+深掘り解説でお届けします。
この記事の目次
ロシアの補給線は1万キロの悪夢だった
ロシアは満洲へ兵力を送るため、はるばる1万キロも離れた本国からシベリア鉄道で補給を行いました。しかし鉄道は単線で、物資は常に大渋滞。前線には食料も装備も届きませんでした。
- 黒パンと乾燥魚が主食
- 缶詰は腐敗していることも
- 極寒の戦地で士気は低下
関連記事:自由民権運動とは?明治の国民を熱くした日本民主主義の原点について解説
関連記事:明治時代に設立された国立銀行の役割とは?
日本は港×鉄道×炊事班の連携が強み
一方、日本は港湾と鉄道を連携させ、補給拠点から前線へスムーズに物資を輸送。現地には炊事班が同行し、温かい食事を提供していました。
- 白米・味噌汁・梅干しなど、日本らしい食事
- 缶詰の肉や野菜も配給
- 兵站距離はロシアの「わずか1/5(約1800キロ)」
関連記事:江戸時代と明治時代では何が大きく変化したの?比較してすっきり分かる
戦う前に勝敗は決まっていた?
十分な補給がある日本兵の士気は高く保たれ、一方でロシア兵は飢えと寒さで戦意を喪失していきました。まさに、兵站が戦場の勝敗を左右したのです。
兵站を制する者が、戦を制す。
Q&A:よくある質問
Q. どうしてシベリア鉄道は単線だったの?
A. まだ建設中で、戦争に間に合わなかったためです。完成は戦後でした。
Q. 日本兵の食事は豪華だった?
A. 豪華ではありませんが、温かく栄養のある食事を取れたことが士気に大きな差をつけました。
参考・出典
- 防衛研究所資料室
- 『明治陸軍食糧事情』
- 遠藤倫朗『日露戦争の兵站』
日露戦争、資金調達の戦い 高橋是清と欧米バンカ-たち / 板谷敏彦
▼ショート動画も毎日更新中!
「ほのぼの日本史」YouTubeチャンネルもぜひチェック


-300x300.jpg)




に乗るkawausoさん-300x300.jpg)
-300x300.jpg)