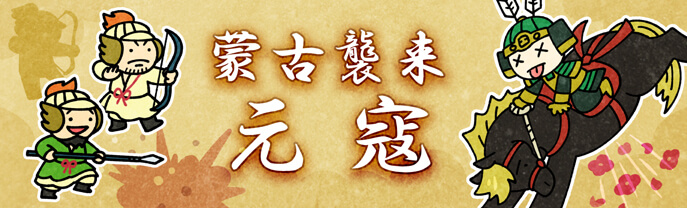踊り念仏で知られる一遍上人は、「熊野(紀伊半島の熊野三山周辺)」で悟りを開いたと言われています。(「熊野成道」)そのため、一遍と熊野とは結びつきが強い印象なのですが、一遍は、熊野だけでなく、「八幡神(やはたのかみ/ はちまんしん)」を祀る八幡宮を頻繁に参詣していたようです『一遍聖絵』や『一遍上人絵伝』に、一遍が各地の八幡宮へ参詣する姿が描かれています。
なぜ、仏教僧侶の一遍は、八幡神に魅せられたのでしょうか。調べてみましたので、ご紹介します。
全国で一番多いけど、日本神話に登場しない八幡神?
まず、注目したいのは「八幡」という名のつく神社や宮社が、日本には如何に多いかということです。日本列島の各地にある神社は、「神社本庁」に登録しているものでは、約8万もあると言われています。その中でも、八幡信仰の「八幡宮・八幡神社」は最も多いようです。その数は約7800社となると言われています。
第二位は、伊勢信仰の系列の神社で、約4400社になるそうです。ただ、国内には、神社本庁に登録していない神社もありますので、それを含めると、約11万かそれ以上となり、八幡神の神社は、4万社ほどにもなると記している資料もあるのです。そして、以下の四社は、有力な八幡宮として知られていますが、いずれも一遍が参詣したと言われています。
①「宇佐神宮(宇佐八幡宮)」(豊前国・現在の大分県宇佐市)
②「大隅正八幡宮」(薩摩国・現在の鹿児島県霧島市)
③「石清水八幡」(山城国・現在の京都府八幡市)
④「松原八幡神社(松原八幡宮)」(播磨国・現在の兵庫県姫路市)
(※中でも、宇佐神宮は、全国の八幡宮の総本社となります。)
八幡神(やはたのかみ/ はちまんしん)とは?
次に、八幡神(やはたのかみ/ はちまんしん)について、簡単に解説します。実は、日本神話には出てこない神なのです。つまり、『古事記』や『日本書紀』には登場しないということです。その由来として、諸説あるようですが、朝鮮半島の新羅の国からやってきた外来の神様という説もあります。
確かなのは、現在の九州の「大分県宇佐」にある「宇佐神宮」が、725年(神亀2年)に創建され、 全国に数多ある八幡神の社の総本宮となっているということです。そして、いつしか、八幡神は、古代の帝の「応神天皇」の化身として、祀られるようになっていたということです。(この「応神天皇」は『日本書紀』では「誉田天皇(ほむたのすめらみこと)」の名で登場します。)
応神天皇は、弓術など武芸に秀でていたとされ、「武の神様」として祀られるようになったそうです。そして、奈良時代の「聖武天皇(701年〜756年)」の代になって、奈良の「東大寺」の大仏が建立されたときに、宇佐神宮がその資材調達のために貢献したということには注目です。さらに、大仏が完成し、晴れて「開眼供養」となったとき、「八幡神」が、その完成を祝い、神輿にのって奈良の都(当時は平城京)に入り、東大寺を参拝したと言われています。
これは、奈良時代では、大仏建立とともに衝撃的な出来事だったと言えます。日本史において、神仏習合の文化が本格的に始まった瞬間と言えるでしょうか。その結果、八幡神が「国家神」の存在に上りつめたようです。さらに、宇佐神宮の影響力は、後に皇位継承問題にまで及んだのです。
そして、鎌倉時代に下り、「元寇【蒙古襲来】(文永の役・弘安の役)」という国家脅威の事態には、朝廷より祈祷を頼まれたというのです。
>>一遍上人は庶民の娯楽を増やした!熊野参詣を広め、芸能人を養成した?
神と仏は一心同体?
次に、八幡神と仏教とのつながりについて見ていきます。先述のように、奈良時代の東大寺大仏の完成のとき、八幡神の神輿が東大寺に参拝したことで、神仏習合の文化が本格的に始まったようです。その証拠となるように、古来「八幡神」の社にある「本地仏(ほんじぶつ)」は、「阿弥陀如来」だと伝えられてきたのです。(※阿弥陀如来とは、大乗仏教の、特に浄土系仏教の尊崇の対象となっている「仏(ほとけ)」の一種です。)
ちなみに、一遍が悟りを開いたと伝わっている「熊野」の本地仏も「阿弥陀如来」だったと言われています。しかも、一遍の在世した時代には、八幡信仰と熊野信仰は同一視されていたと言われていることにも注目です。ですから、当時の常識では、仏教僧侶の一遍が八幡信仰をしても、特に不思議ではなかったのです。
>>熊野信仰の正体とは?歴代上皇も一遍上人も崇拝した熊野信仰の秘密
武家の氏神としての八幡信仰
さらに、鎌倉幕府を開いた初代将軍「源頼朝」と「鶴岡八幡宮」の繋がりの深さにも注目です。
源頼朝は、鶴岡八幡宮を、つまりは八幡神を篤く信仰したと言われています。元をたどると、頼朝の先祖の「源頼義」が京都の石清水八幡宮を信仰していて、鎌倉の由比ヶ浜近くに、氏神として八幡神を祀ったのですが、これが鶴岡八幡宮の創建となるそうです。1063 年(康平6年)のことでした。さらに、頼義の子の「源義家」は、石清水八幡宮にて元服しました。「八幡太郎義家」と言われる所以です。
この義家は、数々の戦乱で武功をあげ、源氏に限らず、武家の棟梁として、後世の武士たちに崇拝されたようです。その義家が篤く信仰した八幡神が、いつしか源氏の氏神から武神の存在として、多くの武士たちから崇拝されるようになったのです。そして、一遍は、元々は、伊予水軍の河野一族という武家の出身になります。一遍の祖父は「河野通信」です。
「源平合戦」では、河野通信は源頼朝に従い、味方しました。その関係で、源頼朝が信仰した八幡神に、河野通信の孫の一遍が、強い繋がりを感じていても不思議なことではありません。
>>伊豆山神社とはどんな神社?北条政子と源頼朝が結ばれた思い出の神社
こちらもCHECK
-
-
源頼朝の死因は落馬ではなく歯周病による脳梗塞?当時は呪いと考えられたってホント【鎌倉殿の13人】
続きを見る
一遍上人の故郷近くの八幡神について
また、伊予国(愛媛県)には、「八幡浜(やわたはま)」という地名があります。奈良時代の養老年間(717年〜724年)には既に、八幡浜と呼ばれていたそうです。この八幡浜は、一遍の故郷(現在の松山市)からそう遠く離れてないのです。約70kmの距離です。当時なら徒歩で2日程度で移動できた距離になるでしょうか。
さらに、八幡浜の近くには、日本一長い岬として知られる「佐田岬」があります(全長約40km)。岬の西端近くには「三崎八幡神社」があり、平安時代前期(860年)の創建になるそうです。その岬から船で西へと向かえば、約16kmの距離で九州に渡ることが可能です(「豊予海峡」)。
現在では、毎日10便以上もフェリーが往来しており、約70分で結んでいます。渡った先は、当時では、豊後国(現在の大分県)です。宇佐神宮が含まれる地域となります。鎌倉時代当時も、この地域間で、それなりの往来があったと推察されます。この地理的環境の点からも、八幡神の存在が、一遍上人の心に大きく根付いていたのかもしれません。
>>水軍の血を引く僧「一遍上人」の壮絶な出生秘話とは?武家の血を継ぐ男の物語
こちらもCHECK
-
-
鎌倉時代の僧「一遍」が遺したのは盆踊りだけではない!一遍上人が未来に残した衝撃の文化遺産
続きを見る
おわりに
そして、一遍上人の在世当時は、「元寇」による脅威がありました。「宇佐神宮」は、九州の「大宰府」の南東部に位置し、100km近くの距離にあります。遠すぎるわけではなく、元寇の脅威を強く感じられる地域だったと言えましょうか。八幡宮の総本社の宇佐神宮は、第二の防波堤の存在だったかもしれません。
「国家神」の八幡神を祀った宇佐神宮を拠点として、加持祈祷が行われ、諸国から九州に集まった武士団は「武神」としての八幡神の存在に励まされ、活躍したと考えられます。その武士団の中に、伊予水軍の「河野通有」や「大友頼康」らがいました。
河野通有は、一遍とは従兄弟の関係でした。また、大友頼康は、一遍を庇護し、経済的パトロンとも言えた存在だったようです。頼康は、豊後国守護を任され、後代の戦国時代に登場した「大友宗麟」の祖先にあたる人物です。当時を生きていた人々の感覚では、宇佐神宮は超がつくほど強いパワースポットであり、そこを中心に国難を乗り切るぞという気概が強かったと考えられます。一遍自身も、その影響下にあったと言えるでしょう。
【了】
【主要参考資料】
・『なぜ八幡神社が日本でいちばん多いのか 』(島田 裕巳 著)幻冬舎新書
・『一遍上人 旅の思索者』(栗田勇 著)新潮社
・『熊野学事始め ヤタガラスの道』(環栄賢 著)青弓社
・『WEBサンガジャパン』より「お坊さん 教えて!第6回 時宗」
・『ニッポンドットコムWebサイト』より「スサノオとヤマタノオロチ伝説、謎の神『八幡神』」
など
こちらもCHECK
-
-
若き日の一遍上人、捨聖への壮絶な道のり【若き日々の秘話を暴く】
続きを見る