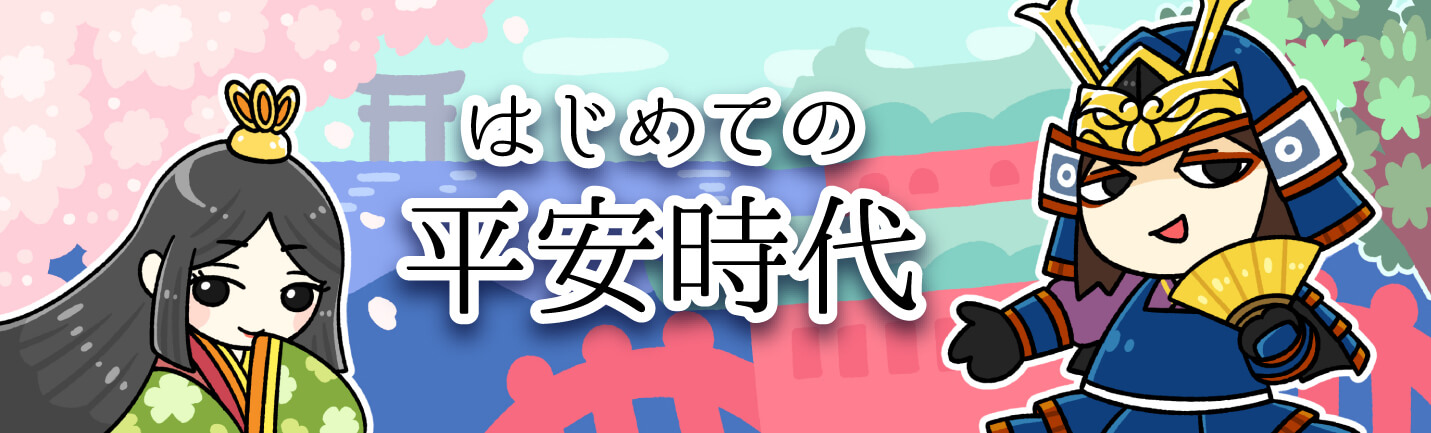NHK大河ドラマ「光る君へ」において、道長の兄として真面目に昇進を重ねているのが藤原道隆です。道隆は右大臣藤原兼家の嫡男であり、藤原摂関家の権力を盤石にする表の役割を期待されていました。いかにも真面目で融通がきかない感じの道隆ですが、史実ではどんな人物だったのでしょうか?
この記事の目次
天暦7年(953年)藤原兼家の嫡男として誕生
藤原道隆は天暦7年(953年)に右兵衛佐、藤原兼家の嫡男として誕生しました。弟の道長より13歳年上で長兄と呼べるポジションです。康保4年(967年)14歳で従五位下に叙されて昇殿を許されます。道隆が年少の頃、父の兼家は兄の兼通に疎まれて不遇の時代を迎えていましたが、貞元2年(977年)に兼通が死去すると返り咲き、2年後には右大臣に就任していました。その頃には道隆は24歳の青年に成長していて、兼家は自分の権力を道隆に継がせるべく手を打っていきます。
こちらもCHECK
-
-
道長のために汚れ役を買って出た、道長パパ[藤原兼家の生涯]
続きを見る
花山天皇の即位で春宮権大夫に就任
兼家は天皇に娘を嫁がせる事に熱心であり、すでに冷泉上皇に娘の超子を入内させて居貞親王(後の三条天皇)をもうけていましたが、円融天皇にも娘の詮子を入内させ懐仁親王を誕生させます。円融天皇の中宮は藤原頼忠の娘の遵子でしたが、遵子は男子に恵まれず、結局、円融天皇の皇子は詮子が産んだ懐仁親王だけでした。
一刻も早く懐仁親王を皇太子にして外戚になりたい兼家は円融天皇に譲位を迫ります。天皇は兼家を信用していませんでしたが、懐仁親王を次の東宮(皇太子)にする事では利害が一致し、要請に応じて永観2年(984年)8月に弟の花山天皇に譲位します。花山天皇は懐仁親王を東宮としました。花山天皇が即位すると道隆は従三位に叙せられて、懐仁親王の春宮権大夫に任じられます。春宮権大夫とは皇太子の御所の政治を取り仕切る役職で宮中を掌握する上で欠く事が出来ないポストです。これは道隆が兼家に信頼されていた事を裏付けています。
こちらもCHECK
-
-
藤原実資とはどんな人?絶頂期の藤原道長に対しても筋を通した公平な人
続きを見る
寛和の変で三種の神器を東宮御所に移す
ところが、天皇に即位した花山天皇は兼家にとっては面倒な相手でした。花山天皇の外祖父は兼家の亡兄伊尹で、伊尹の子の権中納言義懐が天皇を補佐していたのです。このまま放置しておけば、義懐が左大臣・関白になる危険もあり、兼家は一刻も早く花山天皇に譲位させようと計略を巡らしました。そして、この計略には道隆も加担する事になります。寛和2年(986年)兼家は策を講じます。当時、花山天皇は寵愛していた妃を失って落胆し出家を口にしていました。それを聞いた兼家は三男の道兼に命じて花山天皇をそそのかして内裏から山科の元慶寺へ連れ出し出家させてしまったのです。ここで道隆にも出番がやってきます。天皇が消えて宮中が大騒ぎになっている間に、道隆は異母弟の道綱と共に三種の神器を皇太子の御所へ運び込んだのです。
兼家は自分が雇っている源満仲の武士団を出動させて御所の門を警備し邪魔が入らないようにした上で速やかに懐仁親王を一条天皇として即位させました。このクーデタで一条天皇の外祖父兼家は摂政となり、道隆の官位も正三位権中納言から従二位権大納言へ一気に昇進、永延3年(989年)には内大臣に就任します。
こちらもCHECK
-
-
藤原道長とはどんな人?八方美人に徹して権力をつかんだ男【光る君へ】
続きを見る
兼家から権力を継承
永祚2年(990年)正月、道隆は長女の定子を一条天皇の女御として入内させます。自らの権力基盤を強化し始めた道隆ですが、同年5月に兼家が病気の為に関白を辞職すると、道隆は代わって関白へ就任、次いで摂政となります。7月兼家が死去し道隆は家督を引き継いで藤原氏長者になりました。摂関家の頂点に立った道隆は一条天皇に嫁いだ娘の定子を中宮に昇格させます。正暦2年(991年)には内大臣を辞職して弟の道兼に譲りますが、正暦4年(993年)に再び関白に就任、正暦6年(995年)正月には、次女藤原原子を一条天皇の皇太子、居貞親王の妃として後宮へのテコ入れを万全としました。
こちらもCHECK
-
-
NHK大河[光る君へ]初回放送歴代大河最低視聴率!でもこれで良かった理由は?
続きを見る
強引な息子への権力継承
兼家から権力を引き継いだ道隆は、すぐに嫡男藤原伊周の強引とも呼べる引き立てを開始します。永祚2年(990年)10月、道隆が娘の定子を一条天皇の中宮にすると伊周は右近衛中将と蔵人頭を経て、正暦2年(991年)正月に参議に任命され公卿に昇格。同年7月には従三位、9月には異母兄道頼とともに先任参議7名を飛び越えて権中納言に昇進、更に翌年には正三位・権大納言に昇進しました。道隆による伊周の昇進はまだ止まりません。正暦5年(994年)7月に左大臣、源雅信が病死すると、道隆は年長者である藤原道長等3人の先任者を飛び越え、伊周を21歳で内大臣に昇進させました。この時、上席の右大臣は藤原道兼でしたが、伊周の後任の権大納言は伊周の異母兄道頼で、道隆の横暴な人事の独占が際立っています。
いかに藤原氏長者とはいえ、あまりにも身内びいきな道隆の官位引き上げは一条天皇の生母、東三条院詮子や出世を阻害された公卿の不満を募らせました。道隆のあまりに強引な伊周の昇進ラッシュは、大酒飲みでこの頃すでに糖尿病で健康を損ねていた道隆の焦りもあったようですが、道隆死後の伊周への周囲の風当たりを強くし、弟の道長への権力の委譲に繋がる事になります。
こちらもCHECK
-
-
花山天皇(師貞)とはどんな人?藤原氏の陰謀で退位した天皇【光る君へ】
続きを見る
伊周への権力継承ならず
長徳元年(995年)2月、道隆は糖尿病が悪化して重態に陥り、後任の関白に息子の伊周を強く推薦します。しかし一条天皇は道隆の完全な引退を許さず、まず道隆が内覧をおこなった上で内大臣伊周に内覧させるよう宣旨を出しました。これに対して伊周は抗議し、すでに道隆から内覧の業務を引き継ぐ事を委任されているとして宣旨の変更を求めました。
また、この時の宣旨には道隆が病気の間、内覧を伊周が代行すると書かれていましたが、伊周は関白交替が正しいと文書に文句をつけてこれを変えさせようとして失敗します。一連の伊周の傲慢な行動は驕りとして周囲には映り、特に一条天皇の不興を買いました。さらに内覧になった伊周は突如として倹約令を出し、公卿の衣服の裾の長さなど細部に至るまで厳しく制限を加えて統制しようとしたので、公卿から批判の声が上がります。伊周は優秀な人物でしたが、あまりにも急激に昇進したために、政治的センスが未熟で摂関家としてのプライドばかりが高く、それが周囲に傲慢と映ってしまいました。
こちらもCHECK
-
-
藤原道兼の胸糞セリフは真実だった!上級国民だった平安貴族[光る君へ]
続きを見る
伊周への関白継承が叶わないまま死去
道隆は、その後も一条天皇に対し嫡子の伊周への関白就任を強く求めますが、明確な回答が得られないままに長徳元年(995年)憂悶の果てに43歳で死去します。結局、関白は弟の右大臣、藤原道兼が継承しますが、道兼は当時流行していた疫病に感染していて、関白就任から7日間で病死、その後、関白位を巡り、息子の伊周と弟の道長が争いますが長徳の変を契機として伊周は没落。直系子孫に権力を譲ろうとした道隆の願いは叶いませんでした。
こちらもCHECK
-
-
清少納言のエピソードから伝わる清少納言のコンプレックス
続きを見る
日本史ライターkawausoの独り言
大河ドラマでは、真面目で温厚な人物として描かれている道隆ですが、同時代の「大鏡」や「枕草子」によると軽口を好んだ朗らかな人であったそうです。また道隆は大酒飲みで自由気ままな性格をしていて、藤原済時や藤原朝光を飲み仲間として、泥酔して人前で烏帽子を外して髷をさらした話があります。また道隆は整った容貌をしていて、人への気配りが行き届いていたそうです。このように個人としては申し分がない道隆ですが、健康を気にして、息子の伊周への権力移譲を急ぎ過ぎ、伊周に十分な政治経験を積ませないままで内大臣にまで昇進させた事が、周囲の不安と不興を買い、弟の道長が権力を継承するのに道を開いてしまったと言えるでしょう。
こちらもCHECK
-
-
まろの頂点!藤原氏が日本を支配していくまでを徹底解説してみた!
続きを見る