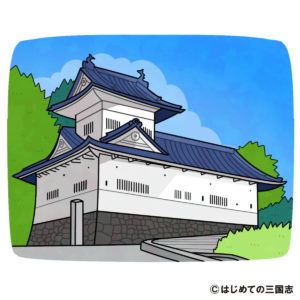父子二代で美濃守護の土岐氏を追放し、国盗りをした戦国大名斎藤道三を知らない人はあまりいないでしょう。その波瀾の生涯は司馬遼太郎の歴史小説、国盗り物語で有名になり、NHK大河ドラマ化され斎藤道三の知名度を全国区に押し上げました。
しかし、美濃の隣国で親子三代で国盗りをした戦国大名の事はあまり知られていません。今回はマムシの道三より上手く下克上したのに、何故か脇役扱いの姉小路頼綱を紹介します。
この記事の目次
飛騨国を親子3代で下克上姉小路氏とは?
今回紹介する戦国大名姉小路頼綱は、元々飛騨国司だった公家の姉小路氏を乗っ取って家名を奪ったもので、本来の姓は三木と言います。姉小路頼綱の祖父、三木直頼は、先祖は多賀氏とも藤原氏とも言われる出自がよく分からない飛騨の一国人でした。
しかし、室町時代に飛騨守護の京極氏や国司の姉小路氏が内紛を起こして衰退した事に乗じ、隣国美濃土岐氏と結んで実力をつけていきます。
やがて、飛騨の南半分を支配し、三木氏が戦国大名化する基礎を築き、土岐頼芸に援軍を出したり、信濃の木曽氏と争うなどその勢力は隣国にまで及んでいきました。
因みに三木直頼は、明応6年(1497年)生まれの天文23年(1554年)没と、隣国の斎藤道三(1494年~1556年)と生没年が近いという類似性を見せています。
飛騨のマムシを継いだ2代目
2代目三木良頼は、永正17年(1520年)飛騨国南部を支配した三木直頼の嫡男として誕生します。そして、天文23年(1554年)に父、直頼が病死した事で三木氏の家督を相続しました。
当時、飛騨国司である姉小路家は、室町中期からの騒乱で3つに分裂していて古川氏姉小路、小島氏姉小路、向氏姉小路と名乗り争乱を繰り返していました。
三木氏は、父の三木直頼時代から小島氏姉小路とは誼を通じていたので、良頼は古川氏と向氏の2つの姉小路を攻撃、弘治2年(1556年)3月、古川氏姉小路家の当主、姉小路高綱を滅ぼし、また、向氏姉小路氏を没落させて、飛騨一国に覇を唱えます。
朝廷工作に抜かりなく三木良頼、下克上達成!
邪魔な姉小路家を排除した後、三木良頼は弘治4年(1558年)室町幕府将軍の足利義輝や、関白の近衛前嗣に接近し、姉小路氏に代わって国司に任命してもらえるように工作し、その甲斐あって朝廷から従五位下・飛騨守に任じられ飛騨国司に就任します。
こうして、名実ともに飛騨の主になった三木良頼ですが、権力だけではいずれ簒奪者として指弾される恐れがありました。
そこで良頼は、滅ぼした古川氏姉小路家に嫡男の三木自綱(頼綱)を押し込んで姉小路家の乗っ取り工作を開始します。朝廷においては、明らかな下克上である三木氏の姉小路家継承について、問題視する声が少なからずありましたが、ここは、剛腕三木良頼の朝廷工作が実を結び、永禄2年(1559年)10月に嫡男の三木自綱が姉小路国司家の一族であると認可されました。
戦国大名には、守護家を乗っ取ったり、家督を継いだりするケースは多いですが、三木氏のように国司の家を乗っ取るケースは珍しいような気がします。三木良頼は、よほど公家のステータスに憧れがあったんですかね?
関連記事:戦国時代のお葬式はどんなだった?現在の葬儀の原型は戦国時代にあった!
中納言の地位を狙うも正親町天皇が拒否
嫡男の自綱が公家である姉小路家を継いだ事で、良頼も姉小路良頼となり官途もトントン拍子に上昇していきます。永禄5年(1562年)2月11日には、良頼は従三位に叙爵、公卿の仲間入りをし、同日に関白近衛前嗣から一字をもらい姉小路嗣頼と名乗りました。
飛騨近辺では比類なき地位を手にいれた姉小路嗣頼は、次に中納言の位を手にいれようとします。理由は、かつての飛騨国司、古川姉小路基綱が従二位、権中納言だった為で、それに並びたかったのでしょう。
そこで、嗣頼は足利義輝や近衛前嗣に奏請してもらいますが、正親町天皇はこれを拒否しました。さすがに無理やり姉小路家に入った氏素性が分からない国人に、中納言まではやれないと思ったのだと推測します。
しかし、姉小路嗣頼には、よほど中納言に執念があったようで、以後は勝手に中納言を自称しました。さらに永禄6年(1563年)3月には、息子の姉小路自綱を侍従とし、引き続き官途上昇を狙っています。
山県正景、木曽義昌の攻撃を受け武田氏に屈従するが…
官途上昇の一方で、北飛騨の江馬時盛との対立は続いていました。永禄年間に入り、甲斐と信濃を支配下においた武田信玄が飛騨国境まで勢力を伸ばすと江馬時盛は武田家傘下に入り、武田家の軍事支援を受けます。
勢い、姉小路嗣頼は、信玄と対立する越後、越中の支配者、上杉謙信と通じました。しかし、永禄7年(1564年)嗣頼は武田家の家臣である山県昌景や木曽義昌の侵攻を受けて降伏、江馬氏に領土の一部を割譲した上に武田氏への屈従を余儀なくされます。
一方でバランス感覚に優れた嗣頼は、元亀元年(1570年)足利義昭を奉じて上洛した織田信長の命令に従い、嫡男の自綱を上洛させて誼を通じさせるなど、武田氏一辺倒ではない狡猾な外交を展開していました。
戦国乱世を巧みに泳いだ嗣頼ですが、この頃から病気がちになり元亀3年(1572年)11月12日に死去しました。父が残した三木氏を大きくし、公卿にまで上る事で権威まで獲得した稀有な名将でした。
飛騨のマムシ3代目姉小路頼綱
姉小路頼綱は、2代目姉小路良頼の嫡男として天文9年(1540年)に誕生します。この姉小路頼綱には、最初から福がついていたようで正室が斎藤道三の娘でした。しかも、この斎藤道三の娘の生母は小見の方であり、つまり、織田信長の正室、帰蝶を通じて頼綱は織田信長と相婿の関係です。
永禄11年(1568年)織田信長が上洛を果たすと、頼綱は父の名代として上洛しますが、飛騨の入り口である加治田城主の斎藤利治と斎藤利堯を通じて、頼綱は信長の親族として扱われました。
この血縁上の幸運は頼綱の生涯の最後まで影響してくるので侮る事が出来ません。
京都では、正親町天皇に拝謁し、足利義昭の居城、二条御所の落成記念の能楽に参加するなど、父に代わり存在感をPRしました。一方で、飛騨に帰国すると病気の父に代わり、上杉謙信の要請に応じて越中に出兵し、上杉氏に通じる姿勢も見せます。頼綱にも、大勢力の間で勢力の均衡を取るバランス感覚が染みついていました。
元亀3年(1572年)11月に父の姉小路嗣頼が死去すると、32歳で姉小路家の当主として家督を継承します。
織田と同盟を結び武断政治を敷く
天正6年(1578年)3月13日、越中を征服する途中の上杉謙信は病没、上杉家中で内部抗争が始まります。これを見て、頼綱は上杉氏を見限り、織田家に接近して同盟を結びました。
天正6年10月14日、織田家の家臣で美濃斎藤氏の斎藤利治を軍団長とする織田軍が飛騨国を通過して越中に攻め込むと、頼綱も越中斎藤氏、斎藤信利、斎藤信吉と共に従軍。
飛騨から茂住峠を越えて、越中に入り月岡野の戦いに参加、今泉城攻城にも従軍しました。この戦いで、織田軍は上杉軍に打撃を与える事に成功し、織田軍弱しという悪評払拭に繋がります、姉小路頼綱は良い仕事をした事になります。
さて、天正9年になると、頼綱は本拠地を桜洞城から飛騨松倉城に移し、飛騨統一に着手します。しかし、この途中、長男の姉小路信綱が実弟の三木顕綱と共謀して謀反を企んだとして誅殺しているそうです。※天正11年(1583年)説もあります。
このように頼綱は飛騨の内外で武断政治を貫き、織田信長の部将、佐々成政の越中における上杉攻めに協力しながら国内の親上杉派を次々と滅ぼしました。
本能寺の変
天正10年(1582年)6月2日、織田信長が本能寺で重臣明智光秀の手に掛かり非業の最期を迎えます。関東から近畿に掛けての織田領内がガラガラポンになる中、飛騨でも北飛騨の有力国人、荒城郡領主の江馬輝盛が勢力拡大を狙い飛騨姉小路宗家、小島氏の小島城に夜襲を掛けました、
夜襲の知らせを聞いた姉小路頼綱は、江馬氏を滅ぼすチャンス到来と、姉小路家の宗家筋である小島姉小路氏の小島時光、小島基頼を同盟軍として、江馬輝盛を八日町の戦いで倒し、さらに、実弟の鍋山顕綱を謀反を計画していたという容疑で滅ぼしました。
以後も、頼綱は鍋山顕綱に関係がある勢力を、過去の味方も含めて次々と打ち滅ぼし、天正11年(1583年)頃には、飛騨一国をおよそ手中に収め統一。その後、家督と居城を次男の秀綱に譲り、自らは北方の高堂城を中心に居を移して隠居生活に入ります。
羽柴秀吉に敵対し戦国大名姉小路氏滅亡
姉小路頼綱は、信長の死後、北陸方面軍だった柴田勝家や越中の佐々成政と行動を共にしていました。
しかし、この判断は頼綱にとって痛恨のミスとなります。信長死後の事態収拾を図った清須会議以後、羽柴秀吉と柴田勝家の関係が悪くなり、賤ヶ岳の合戦が起こり柴田勝家が敗れたのです。
当然、柴田勝家や佐々成政と歩調を合わせていた姉小路頼綱は、秀吉の敵として認識されました。こうして羽柴秀吉の命令を受け、金森長近が飛騨に入り、過去に姉小路氏が滅ぼした旧勢力を先導役にして南北両面から侵攻を開始します。
同盟を結んだ佐々成政は秀吉の大軍に攻められ動けず、孤立無援の姉小路頼綱ですが、降伏勧告を拒否して高堂城で籠城戦します。ところが、その途中、朝廷より城を明け渡すように命令があり姉小路頼綱は降伏しました。
公家であり、また織田信長の親族として秀吉に助命された頼綱ですが、飛騨松倉城で籠城した息子の姉小路秀綱・季綱兄弟や小島時光、小島基頼などは討死や自害で、ほとんどが全滅します。
京都に幽閉された頼綱は、近衛前久や娘婿の遠藤慶隆に生活を援助され、罪人としては、緩い待遇を受けつつ、天正15年(1587年)4月25日に47歳で没します。戦後、飛騨38000石は金森長近に与えられ、戦国大名としての姉小路氏は滅亡しました。
戦国時代ライターkawausoの独り言
初代の三木直頼より、4代半世紀以上も飛騨に大きな勢力を奮った姉小路一族。総石高が小さいので、隣国の美濃や尾張のような大きな合戦は起きていませんが、その中でも姉小路の歴代当主は時代の変化を読み、絶えず生き残りの賭けに勝ち続けました。
しかし、3代目の姉小路頼綱の時代に、秀吉の時代が来る事を見抜けなかった事で、一気に没落の道を辿ってしまいます。
信長の野望では、ショボい能力値の大名として選ばれない確率が高い姉小路頼綱ですが、こうしてみると、もう少し能力値にボーナスポイントがあってもいいような気がします。
関連記事:公家って何?何をした人たちなの?
関連記事:佐々成政はどんな人?戦国アルピニスト肥後国人一揆に泣いた武人の最期