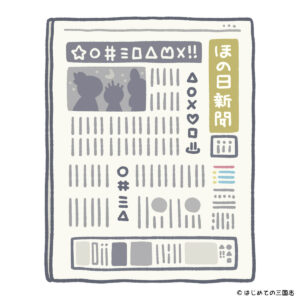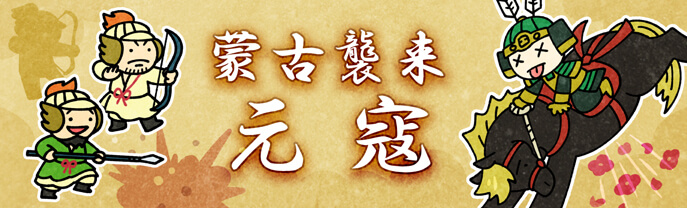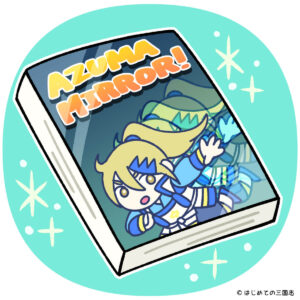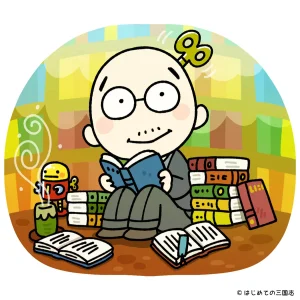鎌倉時代、豊後国(現在の大分県)の守護職に任じられ、元寇では、「鎮西東方奉行」という役職で、日本軍の指揮官として活躍したのが、「大友頼泰」という武将です。
この武将は、鎌倉幕府の重臣の立場でありながら、「一遍上人」に帰依した人物です。そして、この大友頼泰の子孫で、戦国時代に登場した、「大友宗麟」が有名です。大友一族は、代々九州の豊後国を治めていたという印象が強いですが、出身は別の地域でした。今回は、大友一族の発祥と、その子孫について探っていきたいと思います。どうぞご一読ください。
この記事の目次
大友一族の発祥 エピソード0
そもそも、大友氏代々の本拠地は、「相模国(現在の神奈川県)大友郷」という地域でした。頼泰の代になって、豊後国へ移住したようです。ただ、豊後国の守護職を任命されたのは、頼泰の祖父「大友能直」の代からと言われています。
そして、大友能直は、鎌倉幕府初代将軍「源頼朝」の側近でありました。しかし、側近どころか、頼朝の御落胤という説もあるのです。能直の母の「利根局」は、頼朝の元妾だったと言われています。そのため、能直は源頼朝の実子であったかもしれないという説があるのです。実際、大友氏に代々伝わる系図では、頼朝の庶子と記載されているようです。ただ、これは後代、南北朝時代になってから大友一族に箔を付けるために造られたものだという説が有力のようです。
しかし、鎌倉時代、幕府の中枢にいた一族と見てよい訳です。大友氏は、頼朝を始め、鎌倉幕府からの強い信頼があったということです。それは、関東の相模国を故郷とする大友氏が、豊後国の守護職を命じられたことも、一つの大きな理由になるようです。つまり、鎌倉時代初期の当時、九州には平氏の残党が潜伏していた可能性が高かったのです。それらの勢力が結託して再起せぬようにと、監視役を任せられたということになるのです。信頼を置かれていたからこそ、任せられた役職ということになるでしょう。大友氏が平氏残党と結託し、鎌倉幕府に反旗を翻す可能性はないと信頼されていたということです。
ただ、それが頼泰の代になり、「元寇」という国難を迎え、目的が変わっていくのです。
関連記事:元寇で傷ついた武士を救った一遍上人!温泉と念仏で人々を救った驚きの功績
元寇で活躍した大友頼泰について
大友頼泰は、2度に渡る元寇で、「鎮西東方奉行」を務め、日本軍の指揮官として活躍しました。鎌倉幕府からの信頼あっての抜擢だったのです。さらに、頼泰の行動として注目すべきは、流浪の僧侶で、遊行上人と呼ばれた「一遍上人」への帰依も行っていたことです。
頼泰に出会うまでの一遍は、流浪の僧侶として、しかも単独で、諸国行脚をしていた身分でした。ある意味、異端者の存在として見られていたと考えられます。そんな立場の一遍を、幕府の要人だった頼泰は帰依した訳です。周囲を驚かせる出来事だったでしょうし、頼泰の人徳の高さを感じさせることです。
関連記事:大友頼泰はなぜ一遍に心酔したのか?実は大友頼泰は「戦国武将の祖先」だった?
頼泰の亡きあと 将軍家に血を入れた大友一族?
それでは、次に、その頼泰の亡き後、大友一族の動きを見ていきます。特に血筋の流れを見ていきたいのです。すると、興味深い事実が分かってくるのです。
まず、頼泰の娘で、執権の北条家に嫁いだ女性がいました。「北条宗頼」(8代執権「北条時宗」の異母弟)の妻となりました。そして、その孫が「赤橋(北条)守時」であり、「赤橋登子」なのです。
北条守時は、鎌倉幕府の最後の執権であり、赤橋登子は、室町幕府初代将軍「足利尊氏」の妻となった人物です。登子は、室町幕府2代将軍「足利義詮」の母となりました。つまり、大友頼泰の曾孫が、赤橋(足利)登子であり、足利将軍家の母となったのです。
頼泰の血が、鎌倉幕府の北条家の執権にも、室町時代の足利将軍家にも受け継がれたのです。時代を超え、この国の権力の中枢に入り込んできたとも言えるかもしれません。それだけ、大友頼泰という人物が権力側に信頼されていたことを意味していたとも言えるでしょうか。それは、元寇のとき、豊後国の守護職を務め、国難に立ち向かった人物に対する敬意が見えてくるのです。
>>関連記事:北条義時は何をしたことで幕府を掌握し権力を握ったのか?
>>関連記事:鎌倉幕府のあった場所は?現在はどうなっている?そもそも幕府って何?
戦国時代の大友宗麟が、ヨーロッパのキリスト教宣教師たちから王と呼ばれた理由
さて、時代は下り、室町時代末期、所謂、戦国時代に入ると、大友宗麟が登場します。宗麟と言えばキリシタン大名として有名です。
独自にヨーロッパのポルトガルとも外交していたようです。さらに、キリスト教の宣教師たちは、大友宗麟を、豊後国の「王」として見ていたという事実がありました。一地方の大名がなぜ、そこまで持ち上げられたのか?という疑問に対しては、やはり、大友一族の発祥を探ると見えてくるのです。
例えば、大友氏初代の能直が、鎌倉幕府の将軍・源頼朝の実子であったかもしれない説が、当時としては目立つ印象であったことです。その後、鎌倉時代中期の元寇の時には、三代目の頼泰が、指揮官として蒙古軍を迎え撃ち、活躍したこと。さらに、室町時代には、足利将軍家にも血縁で繋がっていたことです。つまり、征夷大将軍を引き継いでもよい立場と見られていたかもしれません。
誇張になると分かっていても、宣教師たちは、宗麟に期待したいという思惑があったのでしょうか。室町幕府の足利将軍家に代わる存在という期待を、宣教師たちは宗麟に持っていたかもしれません。
そして、大友宗麟を中心に、九州にキリシタン国家を立ち上げ、京都の室町幕府を倒した「織田信長」の政権に対峙させようとしていたのか?とも想像してしまいます。
結果、鎌倉時代の元寇の国難を生き抜いた頼泰の功績が影として見えてくるのです。
>>関連記事:鎌倉時代100年分を超分かりやすく圧縮!源平合戦はどのように蒙古襲来に繋がる?【鎌倉殿の13人】
>>関連記事:鎌倉幕府の将軍は源実朝で終わりではなかったってホント?摂家将軍、宮将軍を解説
日本史ライター・コーノの独り言
近代以前、特に江戸時代までは、家柄や血筋が重んじられていた事実がありました。現代では、それを負の面として軽んじる傾向がありますが、過去の事実を探っていく場合、その視点を持つと興味深い事実が見えてくるものです。血筋を追いかけることによって、何故、二つの勢力が争うのか?とか、あるいは結びつくのか?など、解明されていくことがあると思います。
【了】
【主要参考資料】
・『大友能直と河野和泉守 史料で読み解く波多方板山河野氏傳承物語 第二版 』(中山吉弘 著・秀英書房)
・「鎮西探題の成立経過と権限」(みやこ町歴史民俗博物館/WEB博物館「みやこ町遺産」より)
・「大友頼泰公生誕八百年祭開催のお知らせ」より(NPO法人大友氏顕彰会 主催)
・NHK『歴史探偵』
など
>>関連記事:一遍上人は庶民の娯楽を増やした!熊野参詣を広め、芸能人を養成した?
>>関連記事:水軍の血を引く僧「一遍上人」の壮絶な出生秘話とは?武家の血を継ぐ男の物語