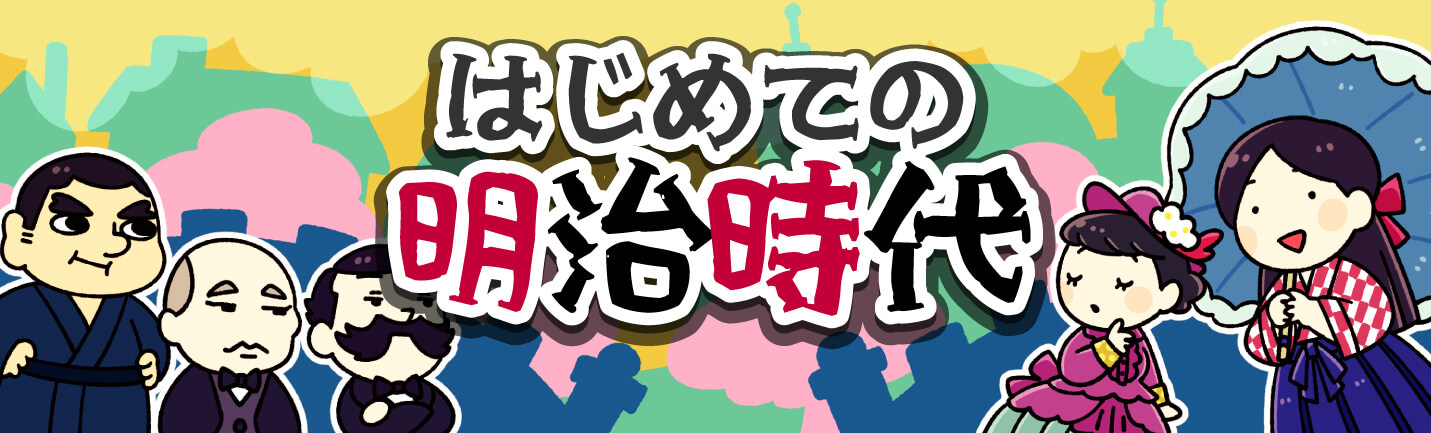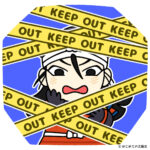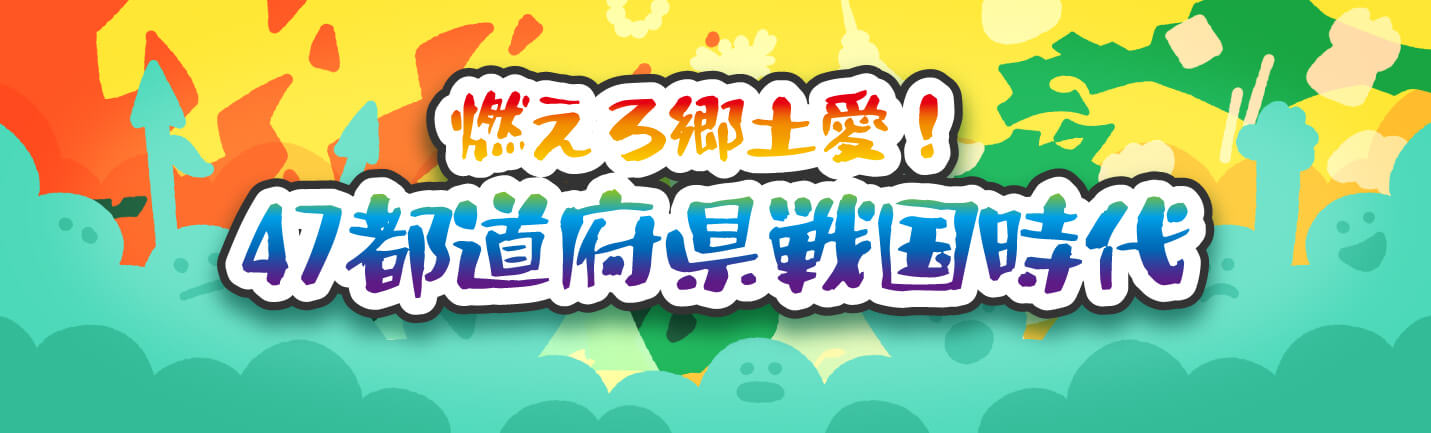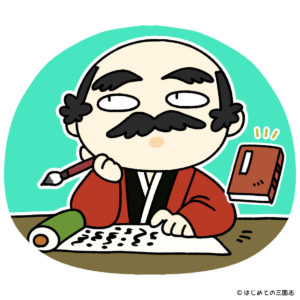
半田銀山は福島県伊達郡桑折町にある廃鉱です。平安時代の大同二年(807年)に発見されたと伝えられ、名前の由来は、金属の接合に使う鉛と錫の合金「はんだ」を語源とする説があるようです。この半田銀山の歴史には戦国の名将、上杉景勝と明治の政商五代友厚が深く関係していました。
この記事の目次
半田銀山の歴史とは
半田銀山は、安土桃山時代の慶長3年(1598年)頃、米沢藩主上杉景勝の時代から本格的な銀の採掘が始まり、その採掘量の多さから、佐渡金山、石見銀山とともに日本三大鉱山といわれました。関ケ原の戦いで上杉景勝が西軍にくみして敗戦すると、寛文四年(1664年)には徳川幕府直轄となり、佐渡金山と同じ組織で運営され、役人も佐渡、岩見、生野から交替で派遣され採掘量も伸びますが半田銀山は産出量が安定せず、江戸時代には操業と停止を繰り返します。採掘が進むにつれて地下水が増大して採掘が困難になり、幕末には操業を停止しました。
明治6年(1873年)鉱山の払い下げが始まり、政商五代友厚が取得して年間約20トンの銀を産出しました。大正、昭和期にも半田銀山は銀採掘を続けていましたが、山の地滑りと半田沼の氾濫で打撃を受け昭和25年には採掘が停止。その後、新しい鉱床も見つからず昭和51年には日本鉱業が採掘を放棄し、平安時代から千年以上続く歴史に幕を下ろします。
こちらもCHECK
-
-
上杉景勝はどうして家康に叛いて西軍に味方したのか?【どうする家康】
続きを見る
五代友厚の銀山改革
半田銀山は銀の採掘量が安定せず、同時に鉱山を掘り進む上で増大した地下水により、幕末には操業が停止されました。明治六年(1873年)日本初の鉱業法「日本坑法」が発布され全国の鉱山は明治政府の独占になりました。翌年からは鉱山の民間への払い下げが始まり、半田銀山は薩摩藩士出身の政商五代友厚が取得し経営を再開します。
五代は日本各地の鉱山を多数所有した鉱山王であり、鉱山経営のノウハウを確立した統括機関を設立。海外から製錬技術を導入して日本各地の鉱山の近代化を進めていました。半田銀山において五代は、海外の最新技術で廃鉱石から銀を取り出すと同時に新たな鉱脈を発見、最盛期には日本一となる年間約20トンを産出します。この半田銀山の利益をもとに五代は「関西財界の父」と称される大活躍をしました。
こちらもCHECK
-
-
五代友厚はどんな人?『青天を衝け』影の主役の生涯につきまとう疑惑
続きを見る
銀山としての成立と発展
半田銀山は、福島県伊達郡桑折町に位置する半田山(標高863メートル)に存在します。記録によると平安初期の大同二年(807年)には発見され、鉛と錫の合金であるハンダ(半田)の名前がついたと言われています。本格的に銀の採掘が始まったのは、佐渡金山を所有していた上杉景勝が伊達郡桑折町を領有してからです。
その後、半田銀山は徳川幕府の直轄地となり、役人も佐渡金山や石見銀山から優秀な人材を投入して採掘量を増やしましたが、採掘量が不安定で閉山と操業を繰り返し幕末には操業を停止しました。しかし、明治六年、鉱山王として知られた五代友厚が明治政府から払い下げられた半田銀山を購入し、欧米の最新の採掘技術と近代的な鉱山経営のノウハウを導入した結果、年間採掘量20トンという日本一の銀を採掘しますが、その後、自然災害で採掘量が減少し、昭和25年(1950年)には休鉱しました。
こちらもCHECK
-
-
渋沢栄一は五代友厚が嫌い?面識はあったの?【東西経済人の真実】
続きを見る
半田銀山を破壊した災害
半田銀山を擁する半田山は、採掘による森林伐採で地盤が緩くなり明治34年から明治36年にかけて大規模な地すべりが頻発、中腹にあった旧半田沼は消滅して南側に現在の半田沼)が出現します。さらに明治43年の豪雨により半田沼が決壊し、山麓一帯が大氾濫を引き起こします。
この時、半田銀山も致命的な被害を受け、大正8年に製錬中止に追い込まれ以後は、採掘した鉱石を売る売鉱に転じていきます。昭和19年、鉱山の経営権が日本鉱業に移りますが、有望な鉱床が見つからないまま休鉱。昭和51年に日本鉱業が採掘権を放棄し、半田銀山の歴史は幕を閉じます。
こちらもCHECK
-
-
渋沢栄一と勝海舟の関係はギクシャク、原因は徳川慶喜
続きを見る
半田沼にまつわる伝説
半田銀山がある半田山の懐には半田沼があり多くの伝説が残されています。一つの伝承では、源義経が平泉の藤原秀衡を頼り半田沼を通ったとき、金銀を背に乗せた赤牛が暴れて沼に落ち、以来、半田沼の主になったそうです。またその赤牛は近くを通る人を襲うので沼には近づかないほうがよいとの言い伝えがあります。その後、赤牛は可愛い娘を妻にしたそうです。このような伝説は危険な沼に子どもが不用意に近づかないように考えられた虚構のように感じますが、黄金の国と呼ばれた奥州平泉と義経伝説、さらに銀山である半田山が連携しているのが興味深いですね。
こちらもCHECK
-
-
源義経の逃げた場所はどこ?悲劇の逃亡ルートに迫る
続きを見る
半田銀山の現在
半田銀山は廃山となり半田沼を中心としてキャンプ場やバンガローが整備されています。また、多くの伝説に彩られた半田沼では ブラック・バス釣りが楽しめ、沼周辺道路はサイクリングロードとして整備され、観光地として生まれ変わりました。
こちらもCHECK
-
-
武田信玄の名言「もう一押しこそ慎重になれ!」言葉の意味と成功者になるための心得とは?
続きを見る
半田銀山の探訪
半田銀山の二階平坑跡を探訪するには、東北自動車道の国見インターで下車し、インター出口を左折、小坂峠方面に進み坂にさしかかる手前で上小坂小学校の前を左折、桑折町方向にしばらく進み カネマン(株)工場の看板まで進んで右折します。そこには材木が積んであり、その左側に二階平坑跡があります。また、半田銀山の鉱石などを展示している旧伊達郡役所へ向かうには、国見インターより国道4号線に出て右折、福島市方面に南下して、 国道4号線より桑折町に入る道路標識から右折すると道なりに旧伊達郡役所があります。
こちらもCHECK
-
-
「鎌倉殿の13人」の黄金はどうして砂金なの?
続きを見る
半田銀山ブルワリーの魅力
半田銀山ブルワリーとは、福島県伊達郡桑折町の特産品の創造を目的としたクラフトビールの醸造施設です。ブルワリーでは桑折町発祥のリンゴ「王林」を使用したジャパン・グレート・ビア・アワーズ銀賞受賞の「王林ペールエール」や銅賞受賞の「半田銀山IPA」など、さまざまなクラフトビールの研究や開発しています。クラフトビールの試飲や飲み比べも可能で、事前に予約すれば工場内見学も出来ます。また半田銀山ブルワリーに併設した上町チアーズはレストランで、ブルワリーで創られたクラフトビールと美味しい食事を一緒に味わうことができます。
こちらもCHECK
-
-
風雲伊達三代、南奥州に地盤を築いた輝宗、輝宗を殺し家督を継いだ政宗、関ケ原直前に生まれた守成の名君忠宗を解説
続きを見る
半田銀山史跡公園へのアクセスと見どころ
半田銀山史跡公園は、半田銀山の各所に残る遺構を集めて公園にしたものです。半田銀山の遺構には、半田山中腹にある江戸中期の手堀り鏨彫りの中鋪坑があり二百年以上も崩落せずに残っています。
また、鉱山から出たズリ(鉱滓)を運搬する専用の貨車が通った軌道跡の石垣や、明治天皇行幸記念碑や銀山役人や多数の銀山坑夫、山師達の無縁墓碑供養碑、各所に残る石臼やズリ、過酷な鉱山作業に従事する工夫を慰労する女郎たちが渡った女郎橋など、半田銀山の歴史の光と影を知る事が出来ます。半田銀山史跡公園へのアクセスは、JR東日本東北本線桑折駅出口から徒歩で23分、または、JR東日本東北本線藤田駅出口から28分です。
こちらもCHECK
-
-
野口英世は左手の火傷で世界史に名を刻む偉人になった!英世を苦しめ飛躍させた手の火傷とは?
続きを見る
半田山登山ルートと自然公園
半田山の登山には3つのルートがあります。一つはキャンプ場登山口でキャンプ場入口になっていて、半田山自然公園管理棟駐車場の近くにあり最も多く利用されています。但しコース中間付近の林間駐車場から先は急な上り坂が続くので注意が必要です。2つ目のルートは南登山口です。
こちらは、北側から管理棟に入る道路沿いで、北口とキャンプ場口の中間地点にあります。登山口を抜けると階段状の急斜面の連続で、20~30分でキャンプ場口からのコースと合流して山頂まで続きます。こちらは、キャンプ場コースの合流点まで急な上り坂が続くため利用する人は少ないようです。3つ目の北登山口は北側から管理棟に入る道路沿いで、駐車場、トイレが設置されています。コースは松林の中でよく整備されていて、ジグザグに急坂を登った先で尾根に取り付くと歩きやすくなります。いずれの登山口も距離が短く、周回コースが取れるので半田山を堪能できます。
こちらもCHECK
-
-
城下町とは何?戦国時代から現代まで続く城下町や企業城下町を紹介
続きを見る
まとめ
半田銀山は平安初期には発見されましたが、戦国時代に上杉景勝により本格的に銀山として開発され、佐渡銀山、岩見銀山と並ぶ日本の三大銀山と呼ばれるほどの銀を産出しました。
江戸時代に入ると、幕府は鉱山の専門家の役人を派遣して銀の増産に勤めますが、技術の限界で半田銀山の銀の産出量は安定せず、採掘の休止と再開を繰り返します。明治時代に入ると鉱山王として知られた五代友厚が半田銀山を買い入れて、西洋の最新の採掘技術を導入して、最盛期には日本一の年間20トンの銀を採掘しますが森林の伐採で明治末には山崩れが頻発し半田沼が長雨で溢れて堤防が決壊し、銀山としての使命を終えました。半田銀山の跡地には、半田銀山史跡公園が整備され、当時の姿を偲ぶ事が出来ます。